ベンチプレス100kgという目標
ベンチプレス100kgかなり無謀な挑戦だと感じる人もいると思います。
私は、50kgから10ヶ月で100kgまで上げるようになりました。
その達成した内容について今回は記事を書きます。
ベンチプレス100kg達成という大目標に向かって、私は単に闇雲に追い込むのではなく、計画的なトレーニング戦略を組みました。
100kgという結果を出すには、トレーニング科学に基づいた計画やトレーニング内容が大切です。
停滞は「努力が足りない」のではなく、神経系や筋肉に蓄積した疲労や技術のズレが原因になっていることが多いと感じました。
そのため、疲労管理とテクニックの修正、そして栄養面の強化を3つの柱とし、この3つを同時に意識して取り組みました。
- 段階的ピリオダイゼーション:強度(重量)とボリューム(セット数やレップ数)を体の適応に合わせて段階的に変化させる
- 戦略的なデロード:4~8週間ごとに疲労回復のための軽めの週を設け、神経系と筋肉をリセット
- 栄養・サプリメント戦略:高強度トレーニングのための炭水化物補給と、クレアチンの継続的摂取
このように各フェーズで何を狙い、どのような刺激を与えるかを明確にした上でトレーニングを組みました。
この記事では、私が実際に行ったトレーニング例に加え、「なぜその負荷やメニューが必要だったのか」という背景を交えつつ、再現性の高い戦略として詳しく解説していきます。
フェーズ1(1~3ヶ月目):神経系の適応とフォーム確立
最初の3ヶ月間は、神経筋接続の最適化とフォームの習熟に全力を注ぎました。
目標は、将来的に高重量を扱う土台を作ることです。
私は週1~2回ベンチプレスを行い、重さはRPE 7~8程度に設定しました。つまり、筋肉が限界に達するまで追い込むのではなく、技術を磨く練習を重視したわけです。
この軽めの強度設定により、爆発的な動作と正確なフォームを意識して反復練習ができました。
この期間、筋力が急激に伸びるのは、筋肉量が増えたからではなく、脳から筋肉への指令の最適化によるものです。初心者ほど、トレーニング開始直後の1~2週間で目に見えて強くなりますが、これは「神経系の適応」=神経のブーストによるもので、その後に筋肉量の増加が追いついていきます。
私も同様に、最初の数週間で扱える重量がグンと伸び、その後は成長ペースが落ち着きました。
これは「神経系の適応期がおしまい、次は筋肥大期へ移行すべき」というサインだと捉えました。
フォーム崩れの防止もこの時期の重要ポイントです。例えばベンチプレスでは手首の過度な反り(リストブレイク)や肘の絞りすぎがフォームを乱します。こうした悪い癖がつくと、後で矯正しづらく、停滞や怪我の原因になるので要注意。私の場合、重すぎないウエイトで週3回の高頻度練習を行い、肩甲骨の寄せ方や肘の軌道を細かく確認しながら動作を繰り返しました。結果的に、このフェーズで「正しいフォームを脳に焼き付ける」ことができ、後の高ボリュームや高重量トレーニングに耐えうる揺るぎない基礎が築けました。
ポイント:
初期の筋力向上は主に神経系の適応。フォームを優先し、スピードを意識した高頻度練習で動きを刷り込むと、後々まで効く基盤になる。
フェーズ2(4~7ヶ月目):筋肥大とトレーニングボリュームの増加
フェーズ1で神経系の進歩が頭打ちになったのを確認したら、次は筋肥大(ハイパートロフィー)を狙ってトレーニング量を増やしました。具体的には、セット数×回数×重量で決まる総トレーニングボリュームを意図的に上げていきます。
- **強度(RPE)**を8~9(あと1~2回余裕)に引き上げ、
- レップレンジを主に8~12回の範囲に設定
このようにして高レップ・高ボリュームをこなすことで、筋肥大に最適な刺激を与えました。
また、補助種目にも注力しました。
ベンチプレスでよく課題になる「押し切り」の強化には、トライセプス強化が有効です。私はケーブルでのプレスダウン(ロープ使用)を取り入れ、上腕三頭筋の外側頭に特に効くよう工夫しました。
ロープを使うと手のひらが向かい合う形になり、下ろしきるときに手のひらを少し後ろに向けることで完全収縮を狙えます。これにより、パワーが抜けやすい上腕三頭筋の弱点を集中的に鍛えました。
さらに、ベンチプレスの押し切りだけでなく、体幹や背中、肩の安定性を高めるために、広背筋や肩の後部(三角筋後部)を鍛える種目も増量しました。
これら大きな支え筋群を強化することで、ベンチプレスのフォームがぶれにくくなり、より重い重量を安心して扱えるようになります。
この高ボリューム期を支えたのがクレアチンのサプリメント摂取です。
クレアチンは短期的に最大筋力を劇的に伸ばすわけではありませんが、高強度の反復回数や総作業量を増加させる効果が知られています。
私は毎日5gのクレアチンを継続的に摂取し、筋肉内濃度を満タンに保ちました。
その結果、疲労困憊に近いトレーニングでも、最後までパワーを維持できるようになり、筋肥大を最大化できました。言い換えれば、クレアチンは「総トレーニング量のブースター」として機能し、次のフェーズである最大筋力期に備える土台を強固にしてくれたのです。
トレーニングポイント:
8~12レップで追い込む高ボリューム期では、ケーブルプレスダウンでトライセプスのロックアウト力を強化し、肩甲骨周りの安定筋も鍛えよう。クレアチン5gはトレーニングのボリュームアップと疲労耐性強化に有効。
フェーズ3(8~10ヶ月目):最大筋力特化とピーキング
フェーズ2までで十分な筋量を獲得できたら、最後の1~3ヶ月目は最大筋力の特化とピーキングを行いました。
この時期の目標は「100kg」を持ち上げるためのパワーに体を合わせることです。
したがって、扱う重量を極限まで引き上げ、レップ数は1~5回の低レップに絞りました。まさにギリギリの重量に挑戦します。
その結果、1回1回のセッションは非常に高強度になります。
しかし、神経系の疲労を考慮し、総ボリューム自体はフェーズ2よりも減らしました。
つまり、セット数を少なくして休みを多めに取り、セッションごとの回復時間を確保しました。
具体的には、ベンチプレス系のセッションではセット間に十分なインターバルを入れ、翌日や翌々日に同じ部位を連続でいじらないように配慮しました。
これにより、限界重量に挑みながらも疲労が過度に蓄積しないようにコントロールしました。
注意点:
高重量フェーズではオーバートレーニングに注意。神経系をリセットし、十分な睡眠と栄養補給で回復を最優先しよう。フォームの乱れが怪我に直結するので、疲労を感じたら軽めに調整する判断も必要。
10ヶ月計画まとめ:主な目標と強度
| フェーズ | 期間目安 | メイン目標 | 強度(レップ数) | フォーカス |
|---|---|---|---|---|
| フェーズ1 | 1~3ヶ月目 | フォーム習熟・神経適応 | 5~8回(RPE 7~8) | 神経系の最適化 |
| フェーズ2 | 4~7ヶ月目 | 筋肥大・ボリューム耐性向上 | 8~12回(RPE 8~9) | 筋肥大促進 |
| フェーズ3 | 8~10ヶ月目 | 最大筋力特化・ピーキング | 1~5回(RPE 9~10) | 特異的筋力向上 |
停滞期克服の戦略:疲労管理とフォーム修正
緻密に計画しても、必ず停滞期は訪れます。とはいえ停滞はマイナスではなく、「身体が出力を一時的に下げてでも回復せよ」と発するシグナルだと私は捉えています。
ここでは、私が実践した二つの主要戦略について紹介します。
戦略的ディロードの実施
長期的に強度の高いトレーニングを継続すると、筋肉だけでなく中枢神経系にも疲労が溜まります。
疲労がリセットされずにトレーニングを続けるとパフォーマンスが落ち、最悪オーバートレーニングになりかねません。
そこで私は、停滞の予兆を感じた段階、あるいは4~8週間連続で成長が見られなかった場合に1週間のディロードを必ず挟みました。
ディロードの方法は状況に応じて二種類。
- 強度ディロード:通常の重さを30~50%に落とし、同じ種目を行う
- ボリュームディロード:重さはキープし、セット数やレップ数だけ減らす
いずれにせよ、いつもより軽く早く・短時間で切り上げることで、筋肉と神経の疲労回復を図ります。
ディロード中は「トレーニングは少しお休み」という感覚で、メンタルもリフレッシュ。実際、最新の研究でもディロード期間が筋肥大を阻害しないことが示されており、長期的には逆に怪我予防やモチベーション維持につながることがわかっています。
停滞を感じたら無理に前に進めず、一度しっかり休むことが“次のステップへの投資”になります。
覚えておくこと:
ディロードは「休憩」ではなく「戦略的一時停止」。
筋肉と神経をリセットして次の高強度に備える重要なプロセスと位置づけよう。
フォーム再評価と技術修正
ディロード中や停滞期には、フォームの見直しも重点的に行いました。
ベンチプレスでは特に「手首の反り」に注意が必要です。私の場合、重さが増すとどうしても手首が反ってしまい、手首痛や力のロスが起こりがちでした。これを修正するため、以下のような練習を取り入れました。
- バンドを使ったフォーム練習:ベンチ台の下にチューブ(バンド)を置き、握ったバーと手首と肘を一直線に近づける意識でベンチプレスを実施。間違ったフォーム(肘を絞りすぎる)だとバンドのテンションが弱くなるため、正しい動きだけが自然と残る感覚を体に覚えさせました。
- 可動域の確保:疲れているとつい浅い動きになりがちですが、フルレンジで胸までしっかり下ろすことで筋肉に新鮮な刺激を与え、停滞を打破します。私はデッドリフトなどでも同じ意識でスクワットやベントオーバー行い、可動域を意識する癖をつけました。
これらのフォーム修正により、停滞中に見逃しがちな小さなズレを修正でき、パフォーマンスが再び上向くことを実感しました。
技術チェックリスト:
- 疲労管理:4~8週で1回、重量30~50%でデロード
- フォーム:バンド練習で拳と肘のラインをチェック、常にフルレンジ実施
- 栄養:1日4~6食の分食でエネルギー切れ防止、トレ前後は炭水化物多めに摂取
- 回復:毎日7~8時間の良質な睡眠で成長ホルモン分泌を促進
- サプリメント:クレアチン継続(5g/日)で高強度運動の持久力アップ
燃料補給戦略:栄養とサプリメントでパフォーマンスを最大化
いくら精緻なトレーニングをしても、燃料(栄養)が不十分では効果は半減します。
ここでは、私が実践した栄養戦略を簡単に紹介します。
炭水化物の重要性
ベンチプレスのような高強度トレーニングでは、炭水化物は主なエネルギー源です。
私はトレーニング前と直後を特に意識して炭水化物を多めに摂りました。
トレーニング直後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれる回復の好機です。このタイミングでタンパク質に加え炭水化物(例えばバナナやプロテイン+ご飯)を摂ると、筋肉合成が促進されると感じました。
理由は、トレ直後は筋グリコーゲンが減っているため、その補充とインスリンによる栄養取り込みが活発になるからです。
また、一度にたくさん食べるのではなく1日4~6回の分食スタイルを取りました。
朝・昼・晩の3食の間に間食やプロテインスナックを挟んでエネルギーとアミノ酸の供給を途切れさせないようにしたのです。高ボリューム期(フェーズ2)では、エネルギー不足で力が出ないと筋分解が進みがちなので、こまめな栄養摂取は非常に効果的でした。
クレアチンの活用
前述のように、クレアチンは私のトレーニングにおいて必須のサプリでした。
クレアチンは筋肉内に蓄えられてATP再合成を助けることで、高強度運動時の持久力を高める働きがあります。
私はトレーニングを始めた直後から毎日5gを欠かさず摂取し、筋肉内の飽和状態を維持しました。クレアチン摂取のポイントは継続すること。
すぐに効果が出るわけではなく、体内プールが満たされて初めてパフォーマンス向上が実感できるからです。
タイミングとしては、タンパク質と一緒に摂るのが効率的です。
例えばトレーニング直後のプロテインシェイクに混ぜたり、食後に牛乳や豆乳で溶かして飲んでいました。
食事やプロテインでインスリンが出ることで、クレアチンの筋細胞への取り込みがよりスムーズになります。こうしてクレアチンを活用し、フェーズ2の総トレーニング量を大幅に増やせたことで、最終的な最大筋力強化の基盤をしっかり築けました。
サプリ&栄養豆知識:
- 炭水化物:トレ前後に重点摂取。筋トレの燃料切れ防止と筋分解抑制に役立つ。
- 分食:1日4~6回に分けて食べて、常にエネルギーを補給。回復力アップとトレ頻度維持につながる。
- クレアチン:毎日5g継続摂取で筋中のストックを満タンに。プロテインシェイクなどと一緒に摂ると効果的。
結論:持続可能なトレーニングへの提言
10ヶ月間でベンチプレス100kgを達成できた要因は、一貫したトレーニング計画と徹底した回復管理でした。高重量を追い続けるには、以下のような点が非常に重要だと感じています。
- 睡眠の確保:毎日7~8時間の質の良い睡眠を取ること。睡眠中に成長ホルモンが分泌されて筋肉修復が進むため、睡眠不足はどんなトレーニングよりもパフォーマンスを低下させます。疲れていても最低6時間はベッドに横になるようにしましょう。
- ウォーミングアップとクールダウン:毎セッション前に十分なウォームアップを行い、終わったらストレッチやローラーで筋肉をほぐす習慣をつけました。怪我を防ぎ、次回トレーニング時のパフォーマンス維持につながります。
- フォームの継続的チェック:長期間続けるとどうしてもフォームが崩れやすいので、定期的に動画を撮って自分の動きを見直しました。分からない場合は信頼できるトレーナーに診てもらうのが一番確実です。
100kgの達成はあくまでひとつの通過点です。
そこから先もさらに伸ばしていくには、より複雑なピリオダイゼーションや、自分の特定の弱点に特化した補助メニューを導入する必要があります。
しかし、ここまでに紹介した科学的かつ戦略的なアプローチは、誰でも再現可能な基盤になるはずです。
一つの目安として、次に目標を設定する際も、今回の成功体験をもとに計画的にトレーニングを組んでいくことをお勧めします。
これらの経験と戦略が、あなたのトレーニング成功のヒントになれば幸いです。
一緒に目標に向かって頑張りましょう!

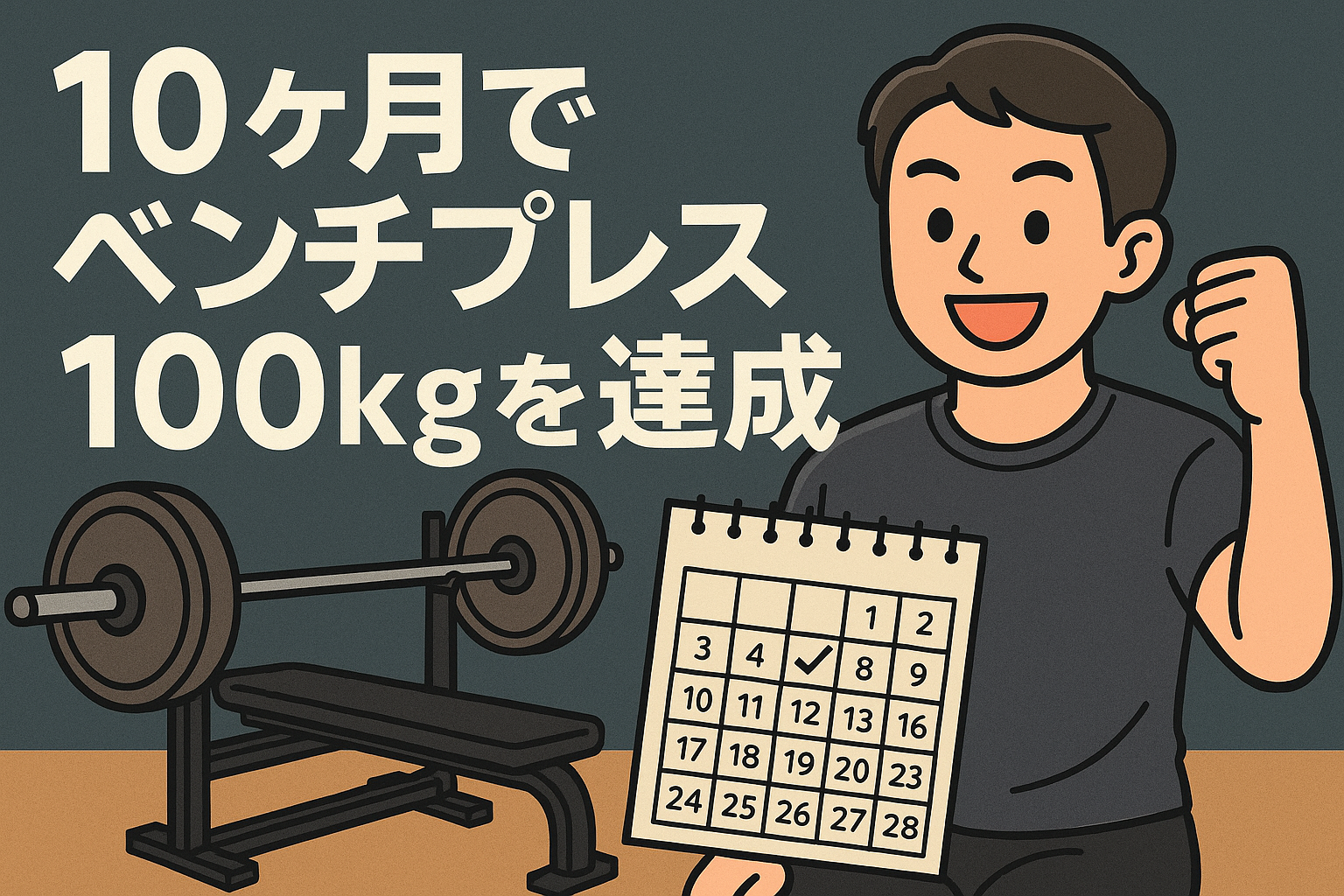

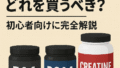
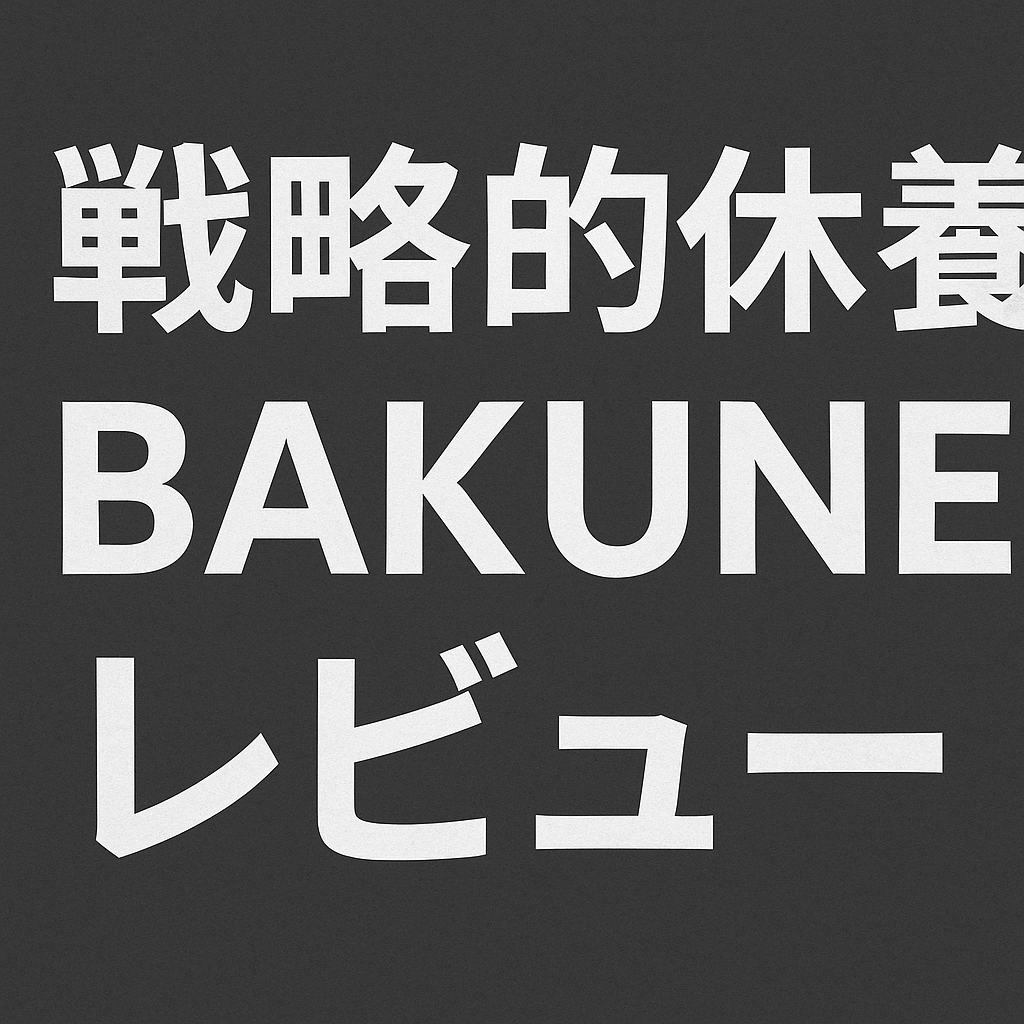


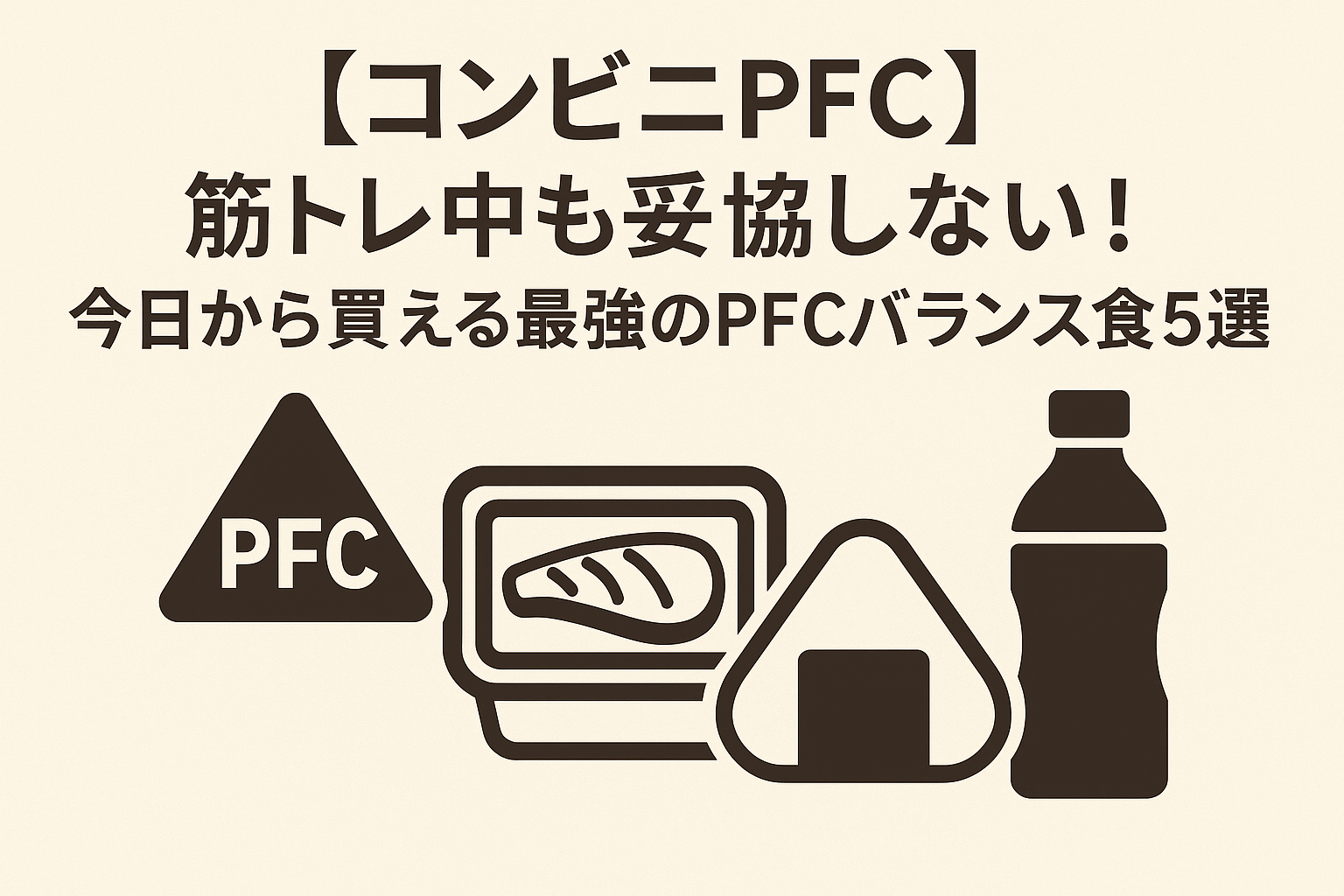

コメント