営業をしていて成果が出ない時期
私は、金融業界の一気通貫の営業からSaaS業界のインサイドセールスに転職し、見込み客への架電やメールを日々行っています。
今回は、インサイドセールスを始めてみたものの、
- 架電してもアポが取れない
- 目標を達成できない
- 転職したばかりで、何から手を付けていいかわからない
――そんな悩みを抱えている方に向けた内容です。
実は私も、入社して2か月間は下記のような悩みで全く成果が出ず、苦しい時期を過ごしました。
- アポが取れない
- KPIは50%で未達
- 架電を躊躇してしまうことがある
しかし、あるポイントを意識してからは毎月KPIを達成できるようになり、達成率を50%から157%まで伸ばすことができました。
そこで今回は、私が成果が出なかった時期にやってしまった失敗を3つ紹介します。
同じように悩んでいる方の参考になればうれしいです。
成果が出なかった時にやってしまったこと3選
ここから私がやってしまっていた3選をご共有します。
1.トークスクリプトに頼りすぎて会話が不自然になった
当時の現状
どの企業や仕事にも、トークスクリプトやロールプレイングを通じて「このように話したら良い」とされる型があると思います。
私の行っているインサイドセールスの業務にも、もちろん存在します。
成果が出なかった時期の私は、何を話したら良いかも分からず、ロープレを通じて作られたトークスクリプトを元に読み上げていました。
「お世話になります。株式会社〇〇のSSです。お忙しいところ失礼します。
私たちは△という商材を扱っており、このようなことが実現できます。御社においても、このようなお悩みはありませんか?」
――このように自社サービスで解決できる悩みに沿って提案し、サービス概要をお伝え。その後にアポ打診をする、という流れを繰り返していました。
「これを続ければ成果は出る」と信じていましたが、実際には全く結果が出ませんでした。相手の反応は薄く、会話がかみ合わないまま終わることばかり。自分でも「こちらの話す割合が高すぎる」と感じていましたし、よく言われる“4不”のうち「不要」を突き付けられるケースが多かったのです。
トーク内容
当時は「プロダクトが良い」と信じていたため、サービスを伝えれば成果につながると考えていました。
その結果、こちらの話す割合が高くなり、4不の「不要」が多発。典型的なプロダクトセリングになっていました。
「どうにかして相手に関心を持って話してもらいたい(=相手の話す割合を増やしたい)」と思い始めてから、会話の流れを変える意識を持ちました。
まず冒頭で「サービスについて覚えていますか?」と投げかけ、Yes/Noで答えられる質問を用意。
Yesであれば仮説提案。Noであれば15秒ほどで端的にサービス概要を伝えるようにして、説明は最小限にしました。
さらに「御社では〇〇のような業務があると思うのですが、その中での××にご関心はございますか?」とボールを投げ、Yes/Noを取る意識を持って会話を展開。
どちらの答えでも次につなげられるようにし、「現状そういった取り組みはされていないとのことですが、そこに課題を感じていらっしゃるということでしょうか?」と問い返すと、相手は自然と自分の状況を詳しく話してくれるようになりました。
さらに「どうなったら理想的ですか?」「今後どうしていきたいですか?」「〇〇様にとって、どんな状態になれば楽になりますか?」と未来志向の質問を重ねることで、相手自身が課題や理想像を語ってくれるようになりました。そこに「当社ならこういった形でご支援できます」と提案すると、以前のような不自然さは消え、アポ打診もスムーズに進むようになったのです。
なぜ失敗だったのか
この失敗の本質は、「相手にメリットのある話ができていなかった」ことにあります。
スクリプトを読み上げることに必死で、「伝えなければ」という気持ちが先行し、相手の声を拾えていませんでした。結果として「会話ができない営業」になってしまっていたのです。
極端に言えば、サービス概要をただ伝えるだけなら、人でなくても良いですよね。そこに気づけたことが大きな学びでした。
改善後の成果
会話の組み立てを「説明中心」から「質問中心」に切り替えたことで、アポ率は大きく改善しました。
入社直後の2か月間はKPI達成率50%にとどまっていましたが、改善後は毎月のKPIを安定的に達成できるようになり、最終的には**達成率157%**を記録できるまでになりました。
数字だけを見ると一気に成果が出たように見えますが、実際には「相手の話を聞く」「質問を工夫する」という小さな改善の積み重ねでした。
まとめ
もし「スクリプトを読んでいるのに成果が出ない」と悩んでいるのなら、それはあなたの能力不足ではなく、“使い方”の問題かもしれません。
スクリプトはあくまで台本。
最初の不安な時期に見るのは良いですが、最終的には「相手との会話」がすべてです。
相手の課題や理想像を聞き取り、「そこで自分はどう役立てるのか?」を伝える。これこそが、私自身が失敗を経て学んだ大切なポイントです。
2.KPIを理解していなかった
当時の現状
転職して間もない当時、私は初めてのリモート勤務、かつ「THE MODEL」と呼ばれる分業型の営業スタイルを理解することで精一杯でした。
当時設定されていたKPIは、有効商談件数・金額、そしてサブKPIとして受注金額。
前職では融資の金額や保険の獲得件数など、契約に至れば評価されるスタンスだったため、「とにかくアポを取れば達成できる」と浅く考えていました。
具体的な失敗エピソード
「アポを取れば良い」と考えていたため、どの状態になれば件数や金額が達成できるのかを理解できていませんでした。
さらに進捗のモニタリング方法も分からず、ただアポを取ること自体が目的化。たまに取れたアポも「個人的に話を聞きたかった」「導入予定は特にない」といった案件ばかりで、数字にはつながりませんでした。
「頑張っているのに、なぜか数字が積み上がらない」という状態に陥り、2か月目までの私は主要指標をすべて未達で終えてしまいました。
なぜ失敗だったのか
失敗の原因は大きく2つありました。
- 自分の現在地を理解していなかった
- 数字の積み立て方を理解していなかった
KPIを「ただのノルマ」としか見ていなかったことで、活動が手当たり次第になってしまったのです。
改善のきっかけ
改善のきっかけは、エース社員の異動と中途の後輩の入社でした。
少人数チームの中で危機感を抱き、さらに後輩に説明できない自分に焦りを感じたことで、KPIを「上から与えられる数字」ではなく「自分で説明できる数字」として理解し直す意識が芽生えました。
改善後の成果
3か月目以降は、
- 金額を上げるにはどの商談が必要か
- 件数を増やすにはどのリード群に注力すべきか
を逆算し、上司を巻き込みながらPDCAを回しました。
ターゲットやトークを改善し、「質と量」のバランスを意識できるようになったのです。
その結果、入社初期はKPI達成率50%で未達続きでしたが、3か月目以降は安定して100%達成を継続を記録するまでに改善できました。
まとめ
「数字の達成ができない」という悩みがあるなら、KPIの構成要素を誤解している可能性があります。
KPI=ノルマであると同時に、成果を出すための道標です。
数字の意味を理解すれば、追われるものではなく「ゲーム感覚」で取り組めるようになります。
KPIは成果を支える仕組みであり、逆算して日々の行動を管理できれば、成果に直結していくはずです。
3.量と質のバランスを意識できていなかった
当時の現状
インサイドセールスを始めた当時、チームには 月600コール という指標がありました。
私は「この数字さえ達成すれば大丈夫」と考え、1日あたり30コールを目安に活動していました。
また、質も大事だと思い、毎日ロープレを繰り返し、夕方には音声を聞いてもらい30分ほどフィードバックを受けていました。
「量もやってるし質も磨けている。だから成果が出るはず」
――そう信じていたのですが、現実は全く違いました。
具体的な失敗エピソード
実際には、アポはなかなか取れず、取れても「個人的に話を聞きたかっただけ」「導入の予定はない」といったケースばかり。
数もこなし、質も磨いているつもりなのに成果につながらない。
「なんでだろう、頑張っているはずなのに」と、焦りと空回りの日々でした。
なぜ失敗だったのか
今振り返れば、当時の私は 量と質の関係性を誤解 していました。
- 600コールを「ゴール」と思い込み、それ以上やる発想がなかった
- ロープレやフィードバックに頼りすぎ、実際の顧客との会話の場数が不足していた
つまり、質を高めれば成果が出るはずだと信じすぎて、量を軽視していたのです。
改善のきっかけと成果
3か月目に、「600コールはあくまで目安で、成果を出すにはもっと必要」と気づき、月800コールを目標にしました。
すると自然と会話の経験値が増え、相手に合わせた話し方ができるようになりました。
最初は「断られるのが怖い」と思っていましたが、アウトバウンドは断られて当たり前。
「取れたらラッキー」くらいの気持ちで臨むと、むしろ気が楽になり、行動量を増やすことができました。
結果として、数字は安定して積み上がり、商談化率も改善。ようやく「量の中で質が育つ」という感覚を実感できました。
まとめ
私は「量と質、両方やっているつもり」でも成果が出ない時期を経験しました。
そこで学んだのは、質は量の先にしかついてこないということです。
失敗は怖いし、断られると自信を失うこともあります。
でも、たくさん行動して、たくさん失敗して、そこから改善を繰り返すことで、結果的に質が磨かれていきます。
もし今「やっているのに成果が出ない」と感じている方がいたら、それは質が足りないのではなく、まだ量が足りていないだけかもしれません。
量をこなしながら質を育てていく。
この順番を意識すれば、成果は必ず積み上がっていきます。
まとめ
失敗から得た教訓
転職してから、正直に言えば苦しい時期が多くありました。
今でも「どう活動すれば成果につながるのか?」と自問自答しながら日々取り組んでいます。
今回ご紹介した失敗は、
- トークスクリプトに頼りすぎて会話が不自然になった
- KPIを理解していなかった
- 量と質のバランスを意識できていなかった
一見バラバラに見えるかもしれませんが、共通していたのは 「自分視点で動いていたこと」 です。
ここまで読んでくださった方の中には、同じように成果が出ず、苦しい時期を経験されている方もいるかもしれません。
でも、それを「自分の力不足」とは考えないでください。
多くの場合、ただ“やり方”を見直せばいいだけです。
相手や周囲にどう価値を届けられるか、そのスタンスを持つことで見方は変わり、行動も変わっていきます。
もし今回の内容が少しでも参考になれば、ぜひ今日から小さくでも行動に移してみてください。
私も同じように挑戦を続けていきます。
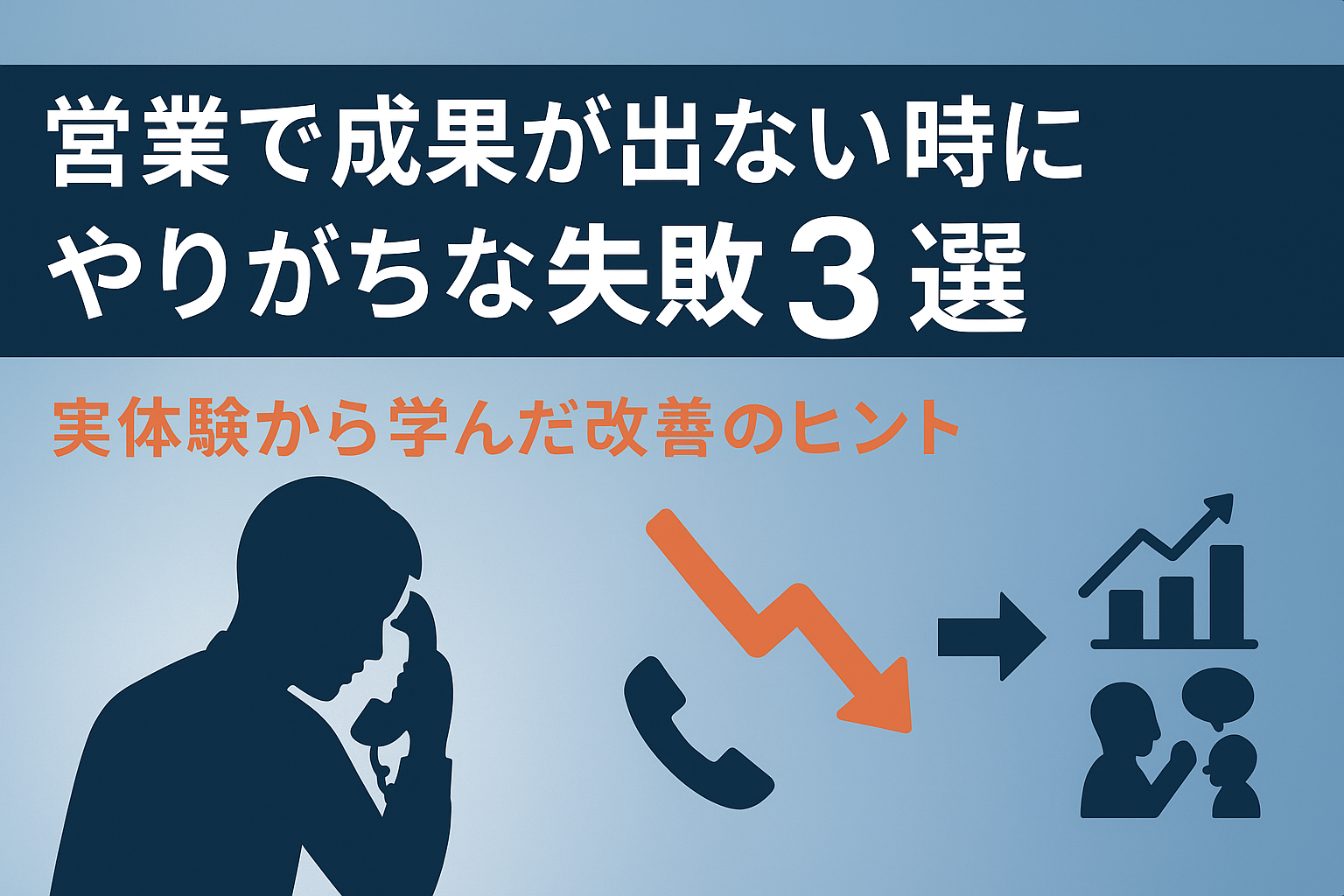

コメント